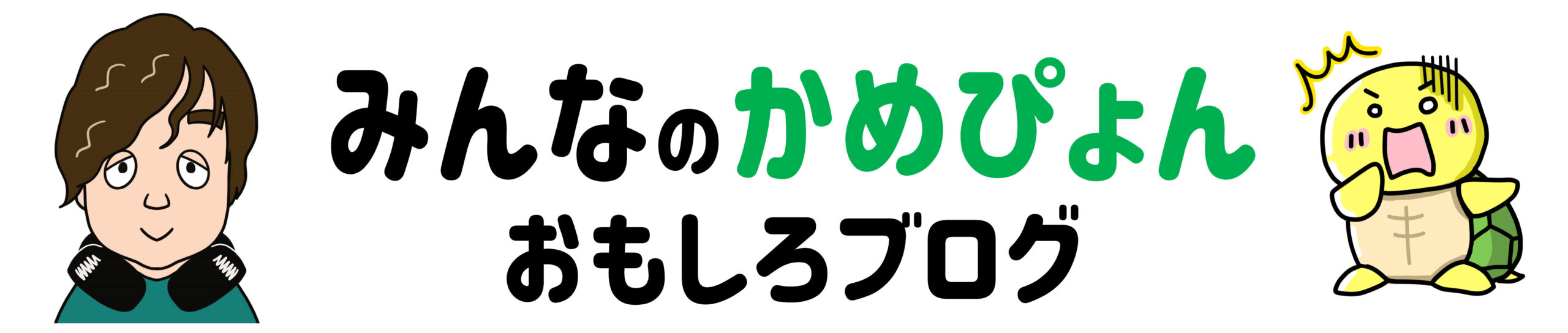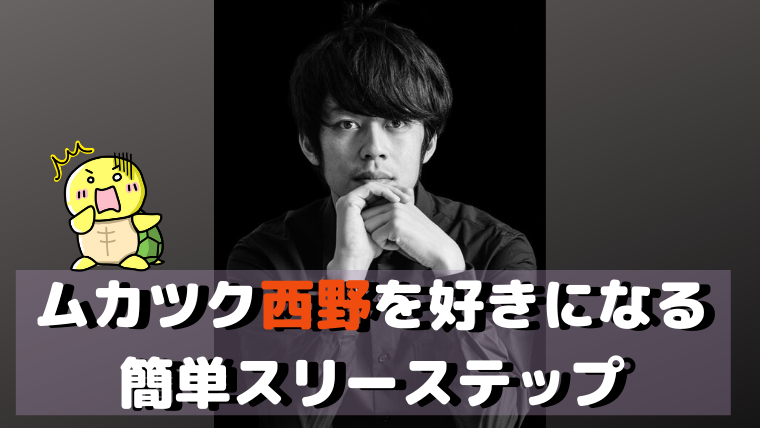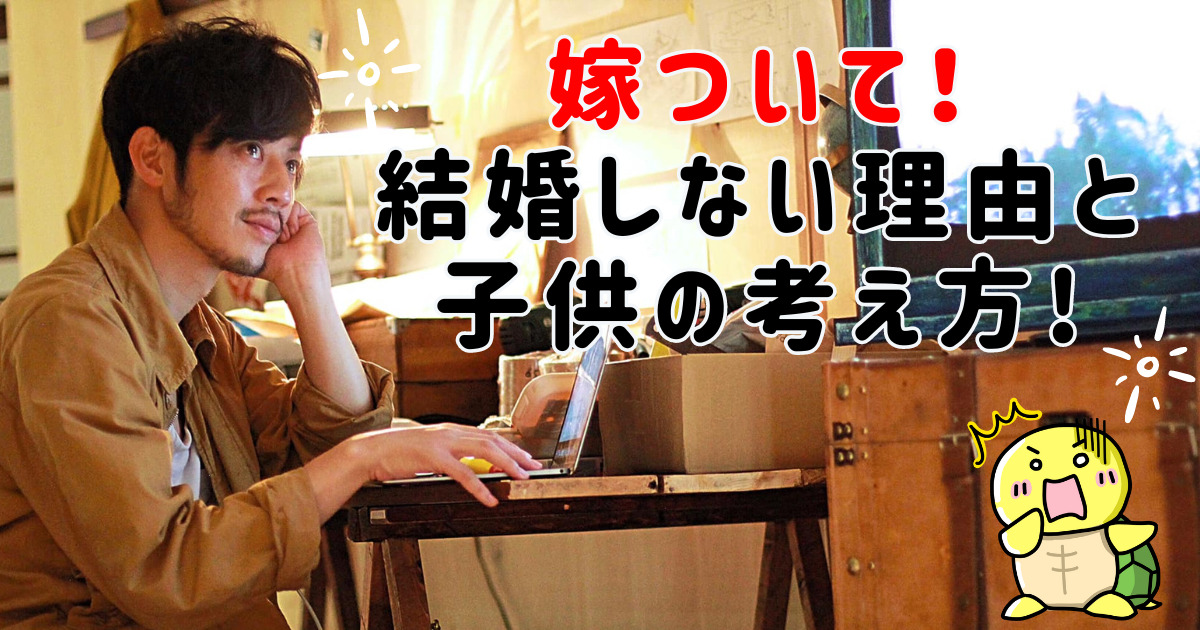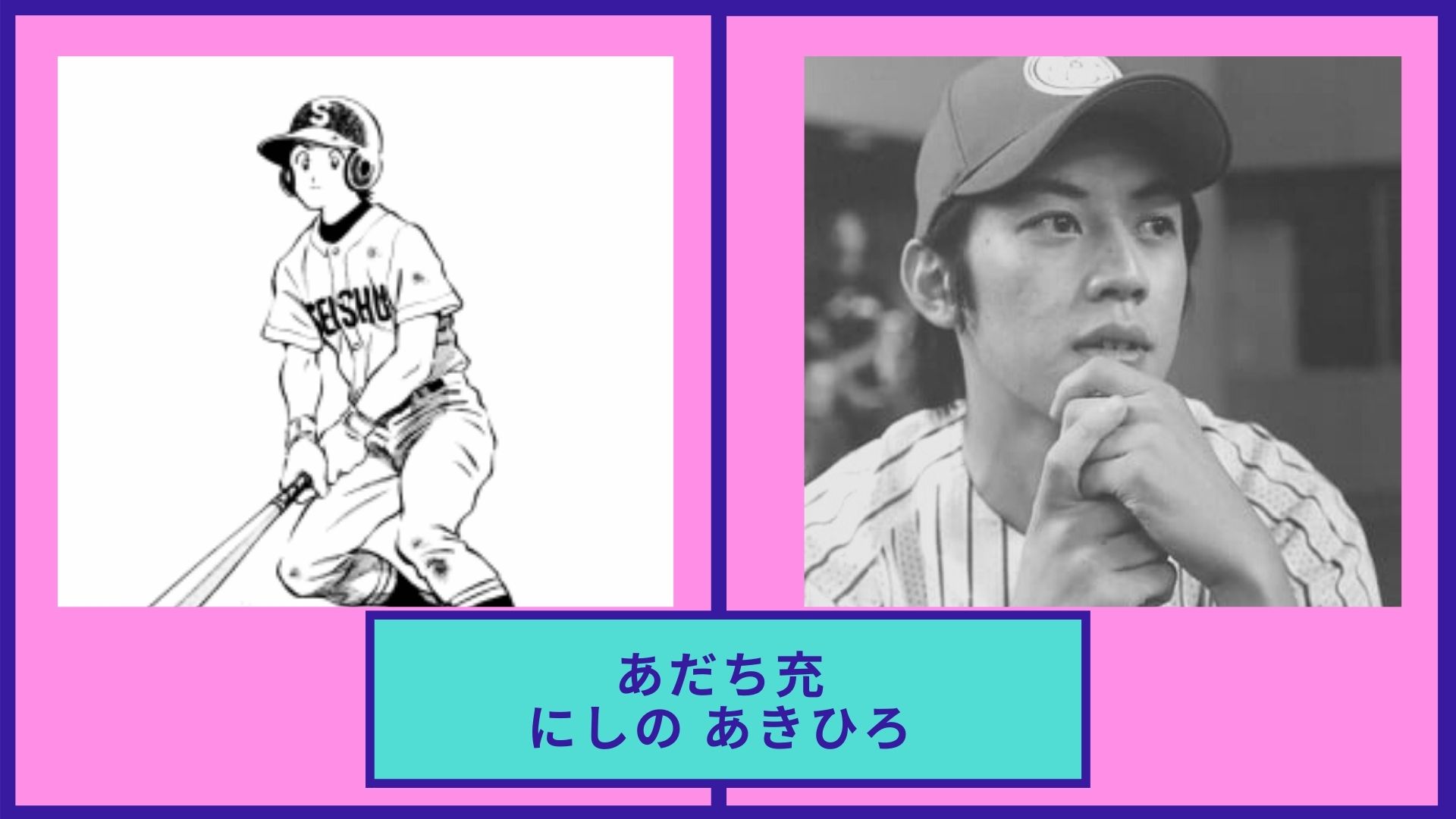レターポットのクソみたいなセキュリティシステムを大暴露!!


2024年に、ほんのりとレーターポットが盛り上がってきております。
レターポットは、2017年にキングコング西野亮廣さんが開発したメールサービスです。
当時は理解不能なサービスでしたが、ブロックチェーン理論やNFT技術の普及により
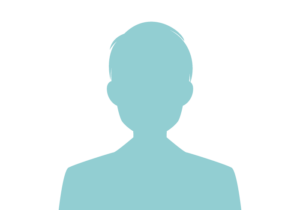
と、なりました、
似てるも何も、レターポットってトークンそのものですから。
つまり、2024年においては「AI技術」など注目されて、みんなのネットリテラシーが底上げされて、レターポットという概念が飲み込みやすい環境に変化したのです。
さて、そこで問題になるのが「セキュリティ問題」です。
レターポットのクソセキュリティシステム
2017年に「新しい通貨」として開発がスタートし、2018年にはあの有名な「コインチェック事件」が起こりました。
コインチェック事件とは、2018年1月26日、外部からのハッキング攻撃を受け、580億円相当の仮想通貨「NEM(ネム)」が盗難された出来事のこと。
複製不能、盗難不能と言われていた仮想通貨(ブロックチェーン技術)ですが、実際にはハッキングによる流出事故が発生してしまいました。
これをきっかけに世間「テクノロジーにおけるセキュリティ」について考えなければいけなくなりました。
当時のレターポットは、まだ「換金できる、できない問題」に揺れていました。
みんな、日本円に換金できると思ってスタートしたレターポットですが、開発途中で

もめにもめていたころです。
まだ換金の可能性もあるのではと揺れていたころです。
そこでは、当然換金できる可能性も視野にいれて開発しなければいけません。
それがコインチェック事件のこともあるし、「不正アクセスの可能性」と「対策に掛かる費用」について、西野亮廣さんも最大限注意しなければいけませんでした。
そして、西野亮廣さんが出した答えは
だから、セキュリティとかなくてよくないっすか?

つまり、「盗んだところで何のメリットもないので誰も盗まない」という、クソセキュリティシステムが採用さました。
意味わかりますか?
お金は信用の担保である
お金は誰からもらっても同じ価値ですよね。
実は、今みたいに「お金を払えば何でも交換できる」という時代になったとのは、割と近代の話なんです。
物々交換の時代であれば、対価に見合わなものしか交換しないやつや、嘘をつく奴は
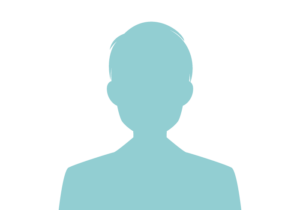
というように、信用がなければ取引停止になってしまいます。
その後、貨幣経済に移行しても、例えば江戸時代なんかでお金より大切なものがあったのです。
それが武士道や職人魂のような「志(こころざし)」です。
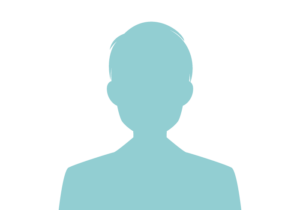
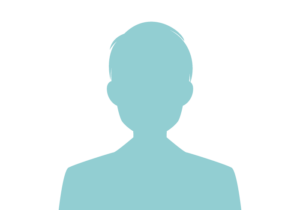
みたいなノリです。
※セリフは完全にかめぴょんの想像です。
しかし、どんどんとお金というものが力をつけていきました。
お金はただのモノやサービスを交換する売価物から、支配の道具になっていったのです。
お金に人が、支配される…
つまり、お金の奴隷です。
お金とは、その人に信用がなくても「お金をちゃんと払ってくれるならいいよ」という、いわば信用の代替品なのです。
お金とは信用であるとよく言いますが、「信用ある人にお金が集まる」とは全く別の意味で、本当に「信用」そのものなのです。
極端な例ですが、「ド田舎にいって、家族経営の町中華でチャーハン食べる」って行動は、初めて行った家で、知らない人が作ったチャーハンを食ったという事です。
普通、知らない人にチャーハン食わせないよね!
普通に考えたら、おかしい行動なのですが「お金」が払われるなら、払う人は別にどんな人でもいいわけです。
お金を払う人に信用はいりません。
なぜなら、お金自体が「信用」だからです。
さて、それではレターポットとはいったい何なんでしょうか?
レターは「誰からもらうか」にしか価値がない
お金は誰からもらっても、誰に使っても同じ価値です。
だから、みんな欲しいし、盗みたくもなるんです。
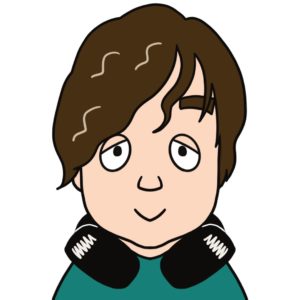
ですが、レターは「誰からもらうか」にしか、価値がありません。
別に、盗んだレターが送られてきても、うれしいはうれしいですが、そもそも論で「レター盗むような人」はコミュニティ内で信用は得られないので、好かれる人にはなれません。
レターは「好かれてる人」からもらうから価値があるのです。
気持ち悪い人から「1文字5円」かけて文字が送られてきたら超絶気持ち悪くないですか??
ってか、レター盗むやつとか絶対キモイじゃないですか?
なので、レターをいくら盗もうが「使う人に信用がなければ盗む意味がない」
盗む意味がないので、セキュリティ不要という鼻くそセキュリティシステムが採用されています。
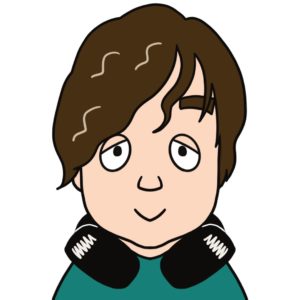
レターポットは、「謎のサービス過ぎて、人に何かを考えさせるきっかけになる」というのがアートっぽいところですよね。